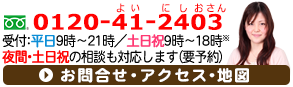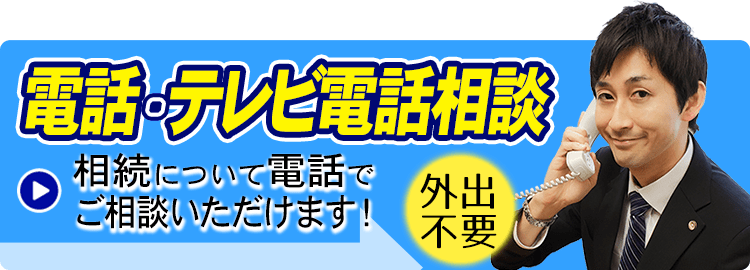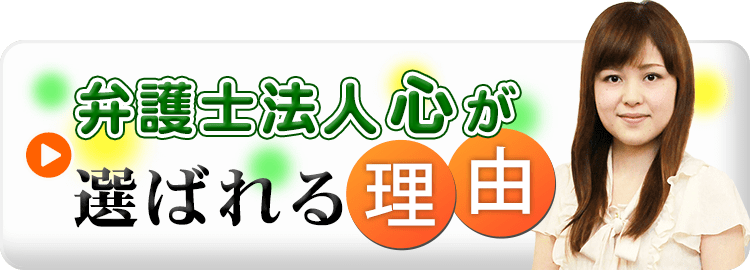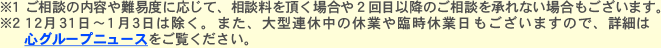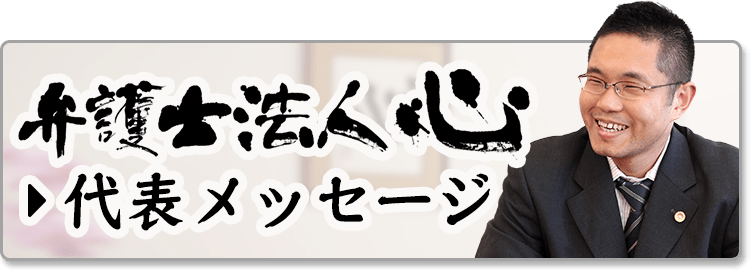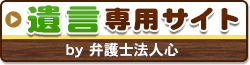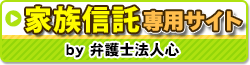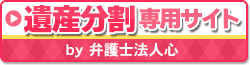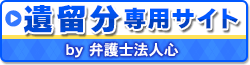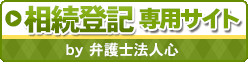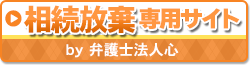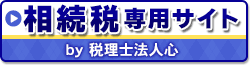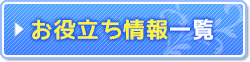遺産の使い込みが判明した場合の対処法
1 遺産の使い込みへの対応方法
被相続人がご存命であるうちに、同居していた相続人などが、被相続人の財産を使ってしまうということが現実にはあります。
典型的な使い込みとしては、被相続人の預貯金を勝手に引き出したり、自分の口座に送金したりするというものが挙げられますが、その他にも、被相続人の財産を売却して得られた金銭を使い込むというケースもあります。
いずれにしても、多くの場合、使い込まれる遺産は金銭ですので、使い込みが疑われる場合には、まず被相続人の通帳や入出金履歴を調査することが基本となります。
被相続人の預貯金等に不自然な流出があることが確認された場合には、その他にも証拠を用意したうえで、使い込みをしたと疑われる相続人に対して返還を求めることになります。
返還を求める際には、一般的にはまず直接話し合いをし、話し合いがまとまらないという場合には訴訟を提起することになります。
以下、使い込まれた被相続人の金銭を取り戻す流れについて詳しく説明します。
2 使い込みの調査と証拠集め
1でも少し説明しましたとおり、遺産の使い込みを調査する際には、まず被相続人の通帳や入出金履歴を確認します。
実際に被相続人の預貯金の使い込みが行われている場合、使い込みをした相続人が被相続人の通帳を渡さないことや、処分してしまっていることがあります。
このような場合には、他の相続人が、金融機関等において被相続人の数年分の入出金履歴を取得することで調査が可能となります。
そのほか、被相続人の不動産や動産が売却されている場合には売買契約書、株式などの有価証券が売却されている場合には取引明細書などを取得します。
被相続人の預貯金の引き出しや、財産の売却が行われた時の、被相続人の認知能力を示す資料も重要です。
当時被相続人が高齢であって、認知能力が相当衰えていたにもかかわらず、コンビニのATMで多額の預貯金が引き出されていたり、インターネット経由で株式の売買がなされているというような場合には、被相続人以外の者が関与しているという推測を強めることができるためです。
3 使い込みをしたことが疑われる相続人への返還請求
特定の相続人が、被相続人の遺産を使い込んでいたといえるだけの証拠が揃いましたら、一般的には、まずその相続人と話し合いを行って遺産の返還を求めます。
話し合いに応じない場合や、話し合いをしたものの約束どおりに返還をしないという場合には、不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をすることになります。
判決に至っても返還に応じない場合には、強制執行による回収をします。
いずれの場合でも、ご自分でこれらの返還請求を行っていくことは難しいかと思いますので、遺産の使い込みが疑われる場合にはまず弁護士にご相談ください。